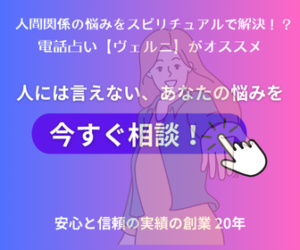インデックス
母への感謝から始まった、私の保育士の夢
小さいころ、保育園に入れなかった私
保育園に通えなかった幼少期の経験が、今の私の原点です。
当時、母は朝から晩まで働いていましたが、保育園の空きがなく、私を預ける場所が見つかりませんでした。
保育園に行けない私は、いつも近所の親戚や母の友人に交代で預けられて過ごしていました。
周りの友だちは保育園でお絵かきや歌を楽しんでいるのに、私は誰かの家で静かに過ごすことが多く、どこか取り残されたような気持ちを抱えていました。
たとえば、年中の時に見た運動会帰りの友だちの写真がとても楽しそうで、母に「どうして私は行けないの?」と聞いたことがあります。
母は「ごめんね。でも、あなたのこと一番に考えてるよ」と涙ながらに答えてくれました。
その時から、保育園という場所が“あこがれ”になりました。
子どもが安心して過ごせて、親も安心して預けられる場所の大切さを、私は身をもって知ったのです。
ひとりで育ててくれた母の姿
朝早くから夜遅くまで働きながら、母はいつも私のそばにいてくれました。
父はいなかったけれど、寂しいと思わせないようにと、母は自分の時間もすべて私に注いでくれていたように思います。
母は、どんなに疲れていても夕食を手作りし、私の話を「うん、うん」と聞いてくれました。
お金に余裕があるわけではなかったけれど、運動会やお遊戯会の衣装を夜中に手縫いで準備してくれたこともありました。
たとえば、小学校の発表会でどうしても赤いスカートが必要だった時、母は持っている布を集めて、徹夜で作ってくれました。
朝になって「できたよ」と笑う母の顔を、私は今でも忘れられません。
そんな母の姿から、私は「誰かを支える強さ」と「やさしさ」を学びました。
そして同時に、親の支えがあって子どもは安心して育つことを、心の底から感じるようになりました。
「困っているお母さんたちを助けたい」そう思ったきっかけ
中学生になった頃、私は自然と「自分はどんな仕事をしたいんだろう」と考えるようになりました。
その時、頭に浮かんだのは、幼い私を支えてくれた母の姿、そして保育園に入れず困っていた母の表情でした。
ある日、近所のスーパーで泣きじゃくる幼児と、それをあやしながら買い物を急いでいる若いお母さんを見かけました。
その姿は、あの頃の母と私の姿に重なって見えました。
「保育園に預けられていれば、きっと少しは楽になれたのに」──そんな思いが胸にこみあげてきました。
その出来事をきっかけに、私は初めて「保育士になりたい」と考えるようになりました。
子どもだけでなく、育児に奮闘するお母さんたちの支えになりたいという思いが、心に芽生えたのです。
たとえば、保育士が子どもを温かく迎えてくれるだけで、朝の別れ際に泣いていた子どもが安心して笑い、お母さんもほっとした顔で仕事へ向かう。
そんな日常のひとコマが、家庭と社会の両方にとってどれだけ大きな意味をもつか、想像するだけで胸が熱くなりました。
子どもと親、両方を支えられる仕事をしたい。
それが、私の夢の原点となりました。
ありがとうを伝えたくて選んだ道
私が保育士という道を選んだ本当の理由は、母に「ありがとう」を伝えたかったからです。
日々の暮らしの中で何度も感謝の気持ちは伝えてきたけれど、母のように誰かを支える人になって初めて、本当の意味で「ありがとう」が言えると思ったのです。
母はいつも「自分の好きなことをしなさい」と言ってくれました。
けれど私は、自分の好きなことだけでなく、誰かの力になれる仕事を選びたいと思いました。
それは、母のように誰かの人生を支えられる人になることでした。
たとえば、進路相談で先生に「保育士になりたい」と話したとき、すぐに「向いてると思うよ」と背中を押してもらえました。
その瞬間、自分の中にあった迷いや不安がすっと消えて、「やっぱりこの道を進もう」と決心することができました。
保育士になれば、子どもと親の両方に寄り添える。
そして、母が私にしてくれたような“安心できる場所”を、今度は私がつくれる。
そう思った時、この道を選んだことに迷いはなくなりました。
この仕事を通して、私は母への感謝を形にしようとしています。
それは、人生をかけて届ける「ありがとう」です。
保育士になるまでの道のり
高校生のときに進路を決めた理由
高校1年生のとき、進路希望調査の用紙を前にして私は「保育士になりたい」と初めて書きました。
それはただの憧れではなく、子どもに関わる仕事がしたいという強い意志でした。
子どもが好きという気持ちだけでなく、幼少期に保育園に通えなかった経験や、母を支えたいという思いが進路の軸になっていました。
どんな道を選べばその夢に近づけるか、高校の進路指導の先生と何度も相談を重ねました。
たとえば、実際に保育士として働いている人の話を聞く機会があり、子どもとの関わり方や職場の雰囲気を具体的にイメージできるようになったことで、私はその場で「やっぱりこの道に進もう」と心を決めました。
また、母が「保育士ってすごい仕事だよ。あなたに向いてると思う」と背中を押してくれたことも、進路決定の大きな後押しになりました。
高校生活の中で少しずつ夢が形になっていくのを実感しながら、私は本気で保育士を目指す覚悟を固めていきました。
専門学校で学んだこと
高校卒業後、私は保育士養成の専門学校に進学しました。
そこでは、ただ子どもと遊ぶだけではなく、成長に必要な知識や関わり方、保護者との連携の大切さまで、幅広く学ぶ必要があることを知りました。
授業では、子どもの発達段階についての理論や、遊びを通して育まれる力、怪我や事故を防ぐための安全管理など、実践に役立つ知識が次々と出てきました。
黒板の前で話を聞くだけではなく、実際に絵本を読んだり、手遊びやピアノの演奏を練習したりと、体を動かす授業も多くありました。
たとえば、音楽の授業では、初めて触れる童謡に合わせてピアノを弾くのに苦労しましたが、何度も練習を重ねて弾けるようになったときの達成感は、今でも心に残っています。
その経験が、自分の中に少しずつ「保育士としての自信」を育ててくれました。
また、グループで課題に取り組む中で、クラスメイトと支え合う大切さや、考え方の違いを受け入れる力も学びました。
保育は、知識と心の両方を育てていく仕事です。
専門学校での学びは、その土台をつくるかけがえのない時間でした。
実習で感じた戸惑いと成長
専門学校での初めての保育実習は、楽しみな気持ちと同じくらい、不安も大きく抱えていました。
理論や授業で学んだことが、実際の現場でどれだけ通用するのか、それを試されるような気がしたからです。
実習先の保育園では、子どもたちが元気いっぱいに走り回っていて、最初はその勢いに圧倒されました。
名前を覚えるのも大変で、思い通りに動いてくれない子どもたちにどう接すればいいのか、戸惑いの連続でした。
たとえば、給食の時間に野菜を食べたがらない子どもに対して、どう声をかければよいかわからず、ただ見守ることしかできなかった日がありました。
その時、担当の先生が「無理に食べさせるのではなく、一緒にお話ししながら気持ちをほぐしてあげて」と教えてくれた言葉が心に残りました。
子どもと向き合うには、正解のない中で一人ひとりと向き合う姿勢が大切だと、実習を通じて実感しました。
また、先生方の言葉や行動から、保育士の仕事には深い観察力と柔らかい心が必要だということも学びました。
戸惑いながらも一日一日を積み重ねることで、自分の中に「もっと学びたい」という気持ちが生まれ、保育の世界に対する理解が少しずつ深まっていきました。
保育士試験とその合格のよろこび
専門学校での学びと実習を終えたあと、いよいよ保育士試験の時期が近づいてきました。
授業でカバーしてきた内容も多くありましたが、それでも試験に向けた勉強は想像以上に大変で、焦りや不安に押しつぶされそうになることもありました。
試験科目は幅広く、保育原理、子どもの発達、福祉制度など、一つひとつをしっかり理解しておく必要がありました。
暗記だけではなく、実際の現場でどう活かされるかを意識しながら取り組むことで、より深い学びに繋がりました。
たとえば、過去問を繰り返し解きながら、自分の理解が浅い分野を重点的に見直すようにしたことで、少しずつ自信がついてきました。
何よりも、「子どもたちのそばで働きたい」という気持ちが、毎日の勉強の原動力になっていました。
試験の結果通知が届いた日、封を開ける手が震えるほど緊張していました。
「合格」の文字を見た瞬間、涙が止まりませんでした。
あの日の喜びは、これまでの努力や思いが一つに報われた瞬間でした。
保育士の資格は、私にとって“夢への鍵”のような存在でした。
それを手にしたことで、自分の人生が大きく動き出すのを感じました。
夢がかなった日
保育士として初めて園の門をくぐった日、制服に袖を通しながら「ついにこの日が来た」と胸がいっぱいになりました。
小さいころから抱いていた夢が、ようやく現実になった瞬間でした。
配属されたのは、0歳から2歳までの子どもたちが通うクラス。
初日は緊張で声がうまく出せず、何を話せばよいのか戸惑いましたが、子どもたちの無邪気な笑顔に迎えられて、自然と表情がほぐれていきました。
たとえば、まだ言葉がうまく話せない子どもが、私の膝にちょこんと座ってきた時、「この子にとって、私はもう“安心できる人”になれたのかもしれない」と思い、感動で胸が熱くなりました。
慣れないことも多く、先輩の保育士に教えてもらいながらの毎日でしたが、保育の現場に立つことで学びが深まり、「この仕事を選んでよかった」と心から思えるようになりました。
母に「保育士になれたよ」と報告した日、母は何度も「よくがんばったね」と言ってくれました。
その言葉を聞いて、私の夢は「自分のため」だけでなく、「誰かの思いに応えるため」にあったのだと、改めて感じました。
夢がかなった日、それは新しいスタートの日でもありました。
そして今も、保育士としての日々が続いています。
保育士の仕事、思っていたのとちがったこと
かわいいだけじゃない、子どもとの関わり
保育士になる前、子どもと一緒に遊んだり、笑い合ったりする姿ばかりを想像していました。
でも、実際に働いてみてわかったのは、子どもとの関わりには“かわいい”だけでは済まされない責任と向き合いがあるということでした。
子どもは一人ひとり個性があり、気分も体調も毎日変わります。
同じ声かけでも、昨日は笑った子が今日は泣き出してしまう。
そのたびに「なぜだろう」と考え、気持ちを受け止めながら向き合う必要があるのです。
たとえば、おもちゃの取り合いで泣いてしまった子どもに対して、ただ「貸してあげようね」と言うだけでは納得してくれないこともあります。
そんなときは、気持ちを代弁しながら、何がいやだったのかを一緒に考え、どうすればよかったのかを伝えていきます。
こうした関わりを通じて、子どもが少しずつ感情を表現したり、人と関わる力を身につけていくのを感じると、大変さの中にもやりがいを見つけられました。
子どもと向き合うことは、ただの遊び相手になることではなく、“心と心を通わせる”ことなのだと気づかされました。
人間関係のむずかしさ
保育士として働きはじめて、子どもとの関わり以上に戸惑ったのが、大人同士の人間関係でした。
職場にはさまざまな年代や考え方の保育士がいて、うまく連携を取るには、技術だけでなく気配りや伝え方の工夫が必要でした。
保育はチームで行う仕事なので、連絡ミスや小さな行き違いが子どもや保護者に影響してしまうこともあります。
そのため、日々の会話やちょっとした報告のタイミング一つでも、関係の良し悪しに影響を与えることがあると実感しました。
たとえば、ある行事の準備中に意見が食い違い、先輩から厳しい言葉をもらったことがありました。
そのときは落ち込みましたが、後から「子どものために真剣だからこそ、厳しい言葉になってしまった」と言われ、保育に対する姿勢を学ぶきっかけにもなりました。
人間関係がむずかしいと感じたときこそ、自分の言葉や行動を見つめ直し、感謝や思いやりをもって接することの大切さを学びました。
保育は、子どもとの関係だけでなく、同じ現場で働く仲間との信頼関係があってこそ成り立つ仕事なのだと強く感じています。
書きものや行事の準備が多いこと
保育士の仕事というと、子どもと遊んだり、お世話をしたりするイメージが強いですが、実はその裏で多くの書類作成や行事準備があることに驚きました。
毎日の連絡帳、保育記録、週案や月案など、子ども一人ひとりの様子を正確に残す書きものは欠かせません。
書く内容は単なる出来事の報告ではなく、「どのような成長があったか」「今後どんな関わりが必要か」など、保育の意図や背景までを考える必要があります。
最初のころは、書くことに慣れていないうえに時間もかかり、帰宅が遅くなる日が続きました。
たとえば、ある日の記録で「泣いていたが落ち着いた」とだけ書いたところ、先輩から「なぜ泣いたのか、どう関わって落ち着いたのかを書いてみて」と助言を受けました。
その一言で、記録は保育士の視点や成長への気づきを残す大切な道具だと気づかされました。
また、季節ごとの行事準備では、装飾づくりや演出のアイデア出し、保護者へのおたより作成など、表に見えない作業も多くあります。
子どもの笑顔の裏には、丁寧な準備と記録が支えていることを知り、保育士の仕事の奥深さを実感しました。
体力が思ったより必要だった
保育士の仕事は、想像していた以上に体力を使う仕事でした。
一日中、子どもと一緒に走り回ったり、抱っこやおんぶをしたり、重たい荷物を運んだりと、体を動かす場面が多くあります。
特に低年齢の子どもたちは、まだ自分でできないことも多く、着替えや食事、トイレなどもすべてサポートが必要です。
一人ひとりに目を配りながら、常にしゃがんだり立ったりを繰り返す毎日は、体のあちこちに疲れがたまっていきました。
たとえば、夏のプールあそびの季節には、気温の中での見守りや着替えの手伝いが重なり、終わる頃には汗だくで立ちくらみがするほどでした。
それでも、子どもたちが「たのしかった」と言ってくれると、その疲れがふっと軽くなるように感じました。
また、インフルエンザの流行期などは、職員が少ない中でクラスを回す必要があり、いつも以上に体力勝負の日々が続きました。
こうした経験を重ねることで、自分なりの体調管理やリフレッシュの方法を見つけることも大切だと学びました。
保育士は心だけでなく、体力面でも強さが求められる仕事です。
けれどその分、子どもの笑顔や成長が、疲れた体を支えてくれる力になります。
それでもがんばれた理由
毎日が慌ただしく、体も心もくたくたになる日もありましたが、それでも私が保育士の仕事を続けられたのは、子どもたちの存在と、支えてくれる仲間の存在があったからです。
どんなに疲れていても、朝「せんせい、おはよう」と笑顔で駆け寄ってくる子どもを見ると、不思議と気力が湧いてきました。
保育の仕事は目に見えにくい努力が多く、うまくいかないことも少なくありません。
けれど、子どもの小さな成長や、「ありがとう」「たのしかった」といった一言が、何よりのごほうびになってくれます。
たとえば、泣いて登園していた子が、ある日、自分から手をつないでくれたとき。
その瞬間、「この子との信頼関係が少しずつ築けている」と感じ、苦労して関わってきた時間が報われたように思いました。
また、職場の先輩や同期の保育士たちが、悩みを聞いてくれたり、「わかるよ」「私もそうだった」と寄り添ってくれたことも、大きな支えになりました。
一人では乗り越えられなかった壁も、誰かと一緒なら越えられる。
そう実感できたことが、私の心を強くしてくれました。
保育士としての毎日は決して楽ではありません。
けれど、その中にある小さな喜びや絆が、私にとって何よりも大きな力となっているのです。
つらい時期を乗りこえて気づいた、大切なこと
はじめての失敗で泣いた日
保育士になって数か月、初めて大きな失敗をした日があります。
それは、ある日のお散歩中の出来事でした。
私が担当していた子が、一瞬目を離したすきに列から離れ、少し離れたところでしゃがみこんでしまったのです。
すぐに気づいて声をかけ、無事に戻ることができましたが、「子どもから目を離さない」という基本を守れなかったことに、自分のふがいなさと責任の重さを痛感しました。
その日の帰り道、情けなくて、悔しくて、涙が止まりませんでした。
その失敗を機に、私は「失敗はしてはいけないもの」と思い込んでいたことに気づきました。
けれど保育の現場では、完璧であるよりも、「気づき」「振り返り」「改善」ができることの方が大切なのだと、あとになって教えられました。
たとえば、他の先生方は「誰にでもあるよ、大事なのは次どうするか」と声をかけてくれました。
その言葉に救われ、私は少しずつ前を向けるようになりました。
失敗を通して学んだのは、責任の重さだけではありません。
子どもを守るという強い気持ちと、学び続ける姿勢が保育士には欠かせないということでした。
先ぱい保育士のやさしい言葉
仕事に慣れはじめた頃、私は自分なりに頑張っているつもりでしたが、うまくいかないことが続いて、自信をなくしてしまった時期がありました。
子どもとうまく関われない日、保護者対応で緊張してうまく話せなかった日、帰り道に何度もため息をついたのを覚えています。
そんなある日、遅くまで残っていた私に、先輩の保育士が声をかけてくれました。
「真莉愛ちゃん、がんばってるね。でも、力を抜くことも大事だよ。子どもって、大人の笑顔に敏感だからね」と、あたたかく微笑みながら話してくれたのです。
その言葉は、張りつめていた心をふっとゆるめてくれました。
それまで私は、すべてを完璧にやらなきゃと思い込んで、自分を追い込んでいたのかもしれません。
たとえば、その先輩は子どもとのやりとりの中でも、いつも自然体で、余裕のある笑顔を見せていました。
そんな姿にずっと憧れていた私は、「保育士って、ただの技術じゃなくて“人としてのあり方”も大事なんだ」と気づくことができました。
その日を境に、私は少しずつ肩の力を抜いて、子どもと自然な関係を築けるようになりました。
誰かの一言が、自分の道しるべになることがある――それを実感した大切な出来事です。
「ありがとう」と言われた日のこと
ある日、いつも朝になると泣いて登園していた3歳の女の子が、珍しく笑顔でやってきたことがありました。
その日はお母さんの仕事の都合でお迎えが遅くなり、夕方までその子と過ごす時間が長くなりました。
私は一日を通して、その子の気持ちをていねいに受け止めながら接するよう心がけました。
おやつの時間も、外遊びも、絵本の時間も、その子のペースに合わせて一緒に楽しむことができました。
そして帰り際、お母さんの姿を見たその子が小さな声で「せんせい、ありがとう」と言ってくれたのです。
たとえば、その子はそれまで、保育園ではなかなか自分の気持ちを言葉にできない子でした。
だからこそ、その一言には、積み重ねてきた信頼と安心感が込められているように思えました。
その瞬間、私は涙がこみ上げるのをこらえながら「また明日も待ってるね」と返しました。
「ありがとう」の一言が、こんなにも心に響くとは思っていませんでした。
保育士という仕事は、目に見える成果がすぐに出るわけではありません。
けれど、こうしたささやかな瞬間にこそ、この仕事の大きな意味と喜びがあると、私は強く感じました。
一歩ずつ成長できるよろこび
保育士として働き始めたころは、毎日の業務に追われるばかりで、自分が何かを成し遂げている実感を持つ余裕はありませんでした。
けれど、振り返ってみると、小さな一歩の積み重ねが確かに自分を成長させてくれていたと気づきました。
たとえば、最初は苦手だったピアノも、少しずつ練習を重ねて、子どもたちと一緒に歌を楽しめるようになりました。
お迎えの時間、保護者にその日の様子を伝えるのも緊張していたけれど、今では自然に会話できるようになりました。
そんな“できなかったことが、できるようになった”という実感が、私の自信になっていきました。
保育の現場では、失敗や反省もつきものですが、その中にこそ学びがあり、次の行動に生かすチャンスがあります。
「昨日より今日、今日より明日」という気持ちで、ほんの少しでも前に進めたときのよろこびは、何にも代えがたいものでした。
子どもたちもまた、日々少しずつ成長していきます。
その姿を見守ることができる仕事だからこそ、自分自身の成長にも素直に向き合えるのかもしれません。
保育士という仕事は、誰かの成長と、自分の成長が、寄り添いながら進んでいくものだと私は思います。
仲間がいたから続けられた
つらい時期を乗り越えることができたのは、いつもそばにいてくれた仲間の存在があったからです。
保育の現場は、体力的にも精神的にも大きな負担がかかりますが、一緒に働く仲間と気持ちを共有できることが、どれほど救いになるかを日々感じてきました。
仕事が終わったあと、職員室で「今日ちょっと大変だったよね」と話し合える時間。
悩んだときに、何も言わなくても気づいて声をかけてくれる同僚のやさしさ。
そうしたささやかなやりとりの中に、支え合いの温かさがありました。
たとえば、行事の準備で手が回らなくなったとき、「よかったらこれ一緒にやろうか?」と自然に手伝ってくれた先輩がいました。
自分のことだけでも大変なはずなのに、そうやって助けてくれる姿を見て、「私もこんなふうに誰かを支えられる人になりたい」と思うようになりました。
保育士はチームで働く仕事です。
その中で信頼関係が築かれていくことで、安心して自分の力を出せるようになります。
仲間の存在は、ただの同僚ではなく、ともに子どもたちの未来を育てる“同志”のような存在でした。
「自分ひとりでは、ここまで来られなかった」
その思いがあるからこそ、今の自分があると心から思います。
保育士って、こんなにうれしい仕事なんだ
子どもたちの笑顔がくれるパワー
どんなに疲れていても、子どもたちの笑顔を見ると、ふしぎと元気がわいてきます。
保育士の仕事は、朝の「おはよう」から夕方の「またあした」まで、子どもたちの表情に寄り添う毎日です。
なかでも、心からの笑顔を見せてくれた瞬間には、言葉では言い表せないような力をもらうことがあります。
それは、気をつかって出してくれたものではなく、安心と信頼の中から自然にあふれ出た表情だからこそ、胸に深く届くのです。
たとえば、なかなか笑ってくれなかった子どもが、ある日私の手を取って「せんせい、これいっしょにやろ」と話しかけてくれました。
そのときの満面の笑顔に、今まで積み重ねてきた関わりのすべてが報われたように感じました。
笑顔は、子どもたちからの“ここにいていいんだよ”というメッセージのように思えます。
そしてそれは、保育士自身にとっても「この仕事を選んでよかった」と思わせてくれる最大のごほうびです。
子どもたちの笑顔は、何よりもまっすぐで力強いものです。
その笑顔に支えられて、私は今日も保育の現場に立ち続けています。
「先生だいすき」と言われた日
ある日の帰り際、年少の男の子が、私の手をぎゅっと握りながら「先生、だいすき」と小さな声で言ってくれたことがありました。
その一言は、あまりにも突然で、でもとてもあたたかくて、胸の奥がじんわりと熱くなったのを今でも覚えています。
その子は、最初のころはなかなか園に慣れず、朝になると毎日のように泣いていた子でした。
私も、どうすればこの子の気持ちに寄り添えるか悩みながら、少しずつ距離を縮めていきました。
たとえば、毎朝決まった場所で絵本を一緒に読んだり、靴を履くときにそっと背中を押してあげたり。
ほんの些細な積み重ねでしたが、それがこの子にとっての「安心」になっていったのだと思います。
「だいすき」という言葉は、子どもにとっても勇気がいる一言です。
その言葉を私に向けてくれたということは、信じてくれている証であり、心を開いてくれた証でもありました。
保育士として、子どもからの“気持ち”を受け取る瞬間ほど、心が満たされることはありません。
あの時の一言は、今も私の心の支えとなって、前に進む力をくれています。
卒園式で涙したあの子との思い出
卒園式の日、成長した子どもたちの姿を見ながら、私は何度も涙をこらえました。
中でも、特別な思い出として心に残っているのは、年少から年長まで3年間ずっと関わってきた女の子との別れの場面です。
その子は、最初は言葉が少なく、人と関わるのが苦手で、集団の中でもなかなか自分を出せないタイプでした。
私は、その子の気持ちに寄り添いながら、無理をせず、少しずつ安心できる時間を積み重ねるようにしてきました。
たとえば、お絵かきの時間に「せんせいといっしょに描く」と手を引いてくれた日、発表会で初めて大きな声を出せた日。
ひとつひとつの小さな成長が重なって、その子の心が少しずつ開いていくのを感じていました。
卒園式の最後、その子が私のところに走ってきて、涙を流しながら「せんせい、ありがとう。わすれないよ」と言ってくれました。
その瞬間、私の目にも自然と涙があふれました。
何もできなかったように思えた日々も、こうして“誰かの記憶に残る時間”になっていたことを知り、胸がいっぱいになりました。
卒園は、子どもたちの旅立ちであると同時に、保育士にとっても大切な区切りの瞬間です。
あの子との思い出は、今も私の中にあたたかく残っています。
保護者からの感謝の言葉
保育士として働くなかで、保護者の方からいただく感謝の言葉は、思っていた以上に心に残るものです。
それは、子どもの成長を一緒に見守ってきたからこそ、深く通じ合える気持ちだと感じています。
ある日、卒園を控えたお母さんが、帰り際に「先生がいてくれて、本当によかったです」と声をかけてくれました。
その言葉は、ふとした一瞬にかけられたものでしたが、胸の奥にじんと響きました。
たとえば、そのお子さんは入園当初、体調をくずしやすく、登園をためらう日も多くありました。
私は、その日の体調や気持ちに合わせた関わりを大切にしながら、少しずつ信頼関係を築いていきました。
お迎えの時に、毎日短くてもお母さんと話をするよう心がけ、安心してもらえるように努めました。
保護者からの「ありがとう」という一言は、「この先生に子どもを預けてよかった」と感じてもらえた証です。
それは、保育士として何よりも嬉しい瞬間であり、自分の仕事に誇りを持てるきっかけでもあります。
子どもの笑顔とともに、保護者の信頼やねぎらいの言葉は、保育士にとって大切な“支え”になります。
その言葉に何度も励まされながら、私はこの仕事を続けてきました。
日々の中で感じる小さなしあわせ
保育士としての毎日は忙しく、時にはくたくたになることもあります。
けれど、そんな日々の中にこそ、何気ないけれど確かな“しあわせ”がたくさんあることを、私はこの仕事を通して知りました。
たとえば、朝の支度を自分でがんばった子どもが「できたよ」と得意げに話しかけてくれる瞬間。
ケガをして泣いていた子が「もうへいき」と笑って立ち上がったとき。
一緒に歌った歌を、帰り道に鼻歌で口ずさんでいる姿を見たとき。
そうした小さなできごとが、保育士の心をやさしく満たしてくれます。
日々の忙しさに流されそうになるなかで、子どもたちはいつも“今”を全力で生きていて、その姿が私にとっての大きな気づきになります。
「当たり前」に見える時間も、ひとつひとつが子どもの成長とともにある、大切な瞬間なのだと教えられるのです。
特別なイベントや大きな成果だけでなく、毎日の積み重ねこそが、保育の本質であり、やりがいでもあります。
この何気ない“しあわせ”の連続が、私の心をやさしく包み込み、保育士という仕事を続けたいという気持ちを育ててくれています。
保育士を目指す10代のみなさんへ
夢をもつことのすばらしさ
「保育士になりたい」と思ったその気持ちは、それだけでとてもすばらしいことです。
たとえ今はまだ遠く感じても、夢を持つこと自体が、すでに一歩を踏み出しているということだからです。
私は、幼い頃に保育園に通えなかったことをきっかけに、この夢を抱きました。
でもそのときは、自分にできるのかどうか、将来どうなるのかなんて、何もわかりませんでした。
それでも「こんなふうになりたい」という思いが心に灯ったことで、自然と行動が変わっていきました。
たとえば、子どもと接するボランティアに参加してみたり、保育のことを調べたり。
小さな積み重ねが、自分の夢を少しずつ現実のものに近づけてくれました。
夢を持つと、つらいことや悩むことがあっても、進むための力になります。
そしてその夢は、自分だけでなく、誰かの人生に寄り添い、あたたかい影響を与えるものになっていきます。
保育士を目指すという夢には、人の心にやさしく光を灯す力があります。
だからこそ、自信をもって、その夢を大切にしてほしいと思います。
今からできること
保育士を目指しているけれど、「何をすればいいかわからない」と思う人もいるかもしれません。
でも、特別なことをしなくても、今できることはたくさんあります。
それは、小さな興味を大切にすること、身のまわりの子どもに目を向けること、そして日々の生活の中で“誰かを思う気持ち”を育てることです。
たとえば、近所の小さな子どもと話してみる、家族の手伝いをしてみる、絵本を読んで子ども向けの表現にふれてみる。
そんな経験一つひとつが、保育士としての土台になっていきます。
また、身近な保育園や幼稚園の見学をお願いしてみるのもよいでしょう。
実際の保育の現場を見て、「自分はここでどんなふうに子どもと関わりたいか」を考えることが、夢をより具体的にしてくれます。
そしてもうひとつ大切なのは、自分自身の気持ちと向き合うことです。
「なぜ保育士になりたいのか」「どんな保育士になりたいのか」
そうした問いを少しずつ自分の中で整理していくことが、将来の進路を選ぶ時の力になります。
大きなことを始めなくてもかまいません。
今できる小さな一歩が、夢を現実にするはじまりです。
保育士に向いている人って?
「自分は保育士に向いているのかな?」と不安に思うことがあるかもしれません。
けれど、保育士に“こうでなければいけない”という決まった型はありません。
一番大切なのは、子どもを大切に思う気持ちと、人と関わるやわらかい心を持ち続けられることです。
もちろん、明るくて元気な人もいれば、落ち着いていて静かな人もいます。
どちらが良い・悪いということではなく、それぞれの個性が保育の中でちゃんと役立つ場面があります。
たとえば、にぎやかな遊びが得意な先生は子どもたちを元気にし、やさしく話を聞くのが得意な先生は子どもの気持ちを深く受け止められます。
また、保育士は子どもだけでなく、保護者や職場の仲間と信頼関係を築いていく仕事でもあります。
そのためには、自分のことばかりでなく、相手の立場や気持ちに目を向ける姿勢がとても大切です。
もし今、「子どもと関わるのが好き」「誰かの役に立ちたい」「人の気持ちを考えられる人でいたい」と思っているなら、それは保育士に必要な素質です。
向いているかどうかは、自分自身の中にある“やさしさ”や“思いやり”が、少しずつ形になっていくことで見えてきます。
迷った時は、まず行動してみよう
「本当に保育士になれるのかな」「自分に向いているかわからない」
そんなふうに迷う気持ちは、ごく自然なことです。
誰でも、未来のことを考えると不安になります。
でも、迷ったときこそ大切なのは、“頭で考えすぎる前に、小さな行動をしてみること”です。
たとえば、子どもとふれあうボランティアに参加したり、保育園の見学を申し込んでみたり、図書館で保育の本を読んでみることでもかまいません。
実際の世界に少し触れてみると、思っていたイメージとの違いや、自分の気持ちがどこに動くのかが見えてきます。
行動を起こすと、新しい出会いや気づきが生まれます。
「やっぱり好きだな」と思えるかもしれませんし、「違うかも」と思って、また別の道が見えてくることもあります。
どちらであっても、それは“進んだからこそ見えた景色”です。
保育士を目指す道も、いきなり全部が見えるわけではありません。
けれど、一歩ずつ足を前に出すことで、少しずつ道が広がっていきます。
迷いは悪いことではなく、きっかけに変えることができるのです。
まずは小さく動いてみる、それが、未来を切り開く一番の近道です。
あきらめない気持ちが一番たいせつ
保育士を目指す道のりは、決して平らな道ばかりではありません。
勉強が難しく感じたり、実習でうまくいかなかったり、まわりと比べて落ち込むこともあるかもしれません。
けれど、どんなときも大切なのは、「あきらめない」という気持ちを持ち続けることです。
私自身、何度も自信をなくしかけたことがあります。
失敗して落ち込んだ日、できない自分に腹が立った日、それでも一歩をやめなかったのは、「保育士になりたい」という気持ちが心の中にちゃんとあったからです。
たとえば、専門学校の授業でピアノが思うように弾けず、家で何度も練習して、ようやく一曲通して弾けたとき。
「続けてよかった」と、心から思えました。
うまくいかない時期があるからこそ、できたときの喜びは大きくなります。
夢に向かって進む途中には、迷いも、壁も、遠回りもあると思います。
でも、保育士は子どもたちに「がんばる姿」を見せる仕事でもあります。
だからこそ、まずは自分自身があきらめずに歩き続けることが、何よりも大切だと思うのです。
夢がかなうその日まで、自分の気持ちを信じて、あたたかく育てていってください。
その気持ちがあれば、きっと保育士への道はあなたを待っていてくれます。
社会人からでも保育士になれる?転職の道とサポート
働きながら目指す人もたくさん
「今さら保育士なんて、遅いのでは?」そう思っている方がいたら、まず伝えたいのは――決して遅くなんてない、ということです。
実際に、保育の現場には、社会人から保育士を目指して夢を叶えた方がたくさんいます。
そしてその多くが、今までの人生経験を活かして、子どもや保護者とあたたかい関係を築いています。
保育士の資格取得は、働きながらでも十分に可能です。
家庭を支えながら、あるいは別の仕事と両立しながら、少しずつ学びを積み重ねている人も少なくありません。
たとえば、平日は仕事を続けながら、週末や夜の時間を使って勉強を進めたり、通信教育でマイペースに学ぶスタイルを選ぶ人もいます。
大切なのは「今の自分にできる形で進めること」。
その積み重ねが、着実に未来へとつながっていきます。
年齢や経歴に関係なく、保育士を目指すという気持ちは、それだけで立派な第一歩です。
これまでの人生で得た視点や気づきは、保育の現場において、きっと大きな力になります。
資格を取る方法は2つある
保育士になるためには「保育士資格」が必要ですが、その資格を取る道は大きく分けて2つあります。
自分に合った方法を選ぶことで、社会人からでも無理なく挑戦することができます。
ひとつは、保育士養成の専門学校や短期大学などで学び、卒業と同時に資格を取得するルートです。
この方法は、しっかりと時間をかけて基礎から学べるため、実践的な知識や技術を身につけたい方に向いています。
ただし、学校に通うための時間と費用が必要になるため、ライフスタイルに応じて計画を立てる必要があります。
もうひとつは、「保育士試験」に合格する方法です。
こちらは、保育士養成校を卒業していない方でも受験できる国家試験で、学歴や職歴に関係なく挑戦できます。
働きながら学びたい方や、費用をおさえて資格を取得したい方に選ばれています。
たとえば、市販のテキストや通信講座を利用して、自宅で勉強を進める人も多くいます。
試験には筆記と実技がありますが、段階的に合格していくこともできるため、焦らずに取り組むことができます。
資格を取る道はひとつではありません。
自分のペースや環境に合った方法を選べば、夢に近づく一歩を着実に踏み出すことができます。
夜間の学校や通信教育という選択
保育士を目指す社会人の多くが選んでいるのが、夜間の学校や通信教育という学び方です。
働きながらでも無理なく続けられるこのスタイルは、家計や生活リズムに合わせながら資格取得を目指せる、現実的で心強い選択肢です。
夜間の学校では、仕事が終わった後の時間を使って通学することができます。
講師から直接学ぶことで、わからないことをすぐに質問できる安心感があり、仲間と励まし合いながら学べる点も魅力です。
通学の負担はありますが、一定のリズムを持って学習を継続しやすいというメリットがあります。
一方、通信教育は、自宅で自分のペースで勉強できるのが最大の利点です。
仕事や家事、育児などで決まった時間が取りづらい方には、自由度の高い通信講座が向いています。
最近では、動画講義やオンラインでの添削指導など、サポートの充実した通信教材も増えています。
たとえば、週末にまとまった時間を使って学習したり、通勤の電車でテキストを読むなど、日常の中に少しずつ“勉強の時間”を取り入れる工夫をする人もいます。
自分の生活スタイルに合った方法を選ぶことが、学びを続ける大きなポイントです。
焦らず、一歩ずつ積み重ねていけば、社会人でも保育士になる夢は確かに形にできます。
ハローワークや市役所のサポート
保育士を目指す社会人にとって、心強い味方になるのがハローワークや市役所などの公的なサポートです。
「資格を取りたいけど、どうやって始めればいいかわからない」そんな時は、まずこうした窓口に相談してみることをおすすめします。
ハローワークでは、保育士資格取得を目指す人向けに、職業訓練や受験対策講座などを提供していることがあります。
受講料が無料または低額で受けられるものもあり、経済的な負担を抑えながら学習を進めることが可能です。
さらに、条件を満たせば職業訓練受講給付金などの支援を受けられる場合もあります。
たとえば、働きながら資格を取りたいと考えていた知人は、ハローワークの相談をきっかけに受験対策講座を受講し、保育士試験に合格しました。
「一人では不安だったけれど、情報をくれたことで一歩踏み出せた」と話していたのが印象的でした。
また、市役所や地域の子育て支援課などでも、保育士資格取得を後押しする情報が得られることがあります。
なかには、地元での就職を前提に資格取得の費用を一部支援する自治体もあります。
「どこに相談したらいいかわからない」と感じたら、まずは最寄りのハローワークや役所に足を運んでみてください。
新しい情報や、自分に合った制度と出会えるかもしれません。
無料で相談できる支援センター
保育士を目指したいけれど、「一人で進めるのは不安」「何から始めればいいのかわからない」という方には、各地にある保育士支援センターの利用がおすすめです。
これらの支援センターでは、保育士を目指す人や、保育現場での就職を考えている人に向けた無料の相談・サポートが受けられます。
支援センターでは、資格取得までの流れ、試験対策、実習先の紹介、就職情報の提供まで、幅広く対応してくれます。
また、保育士試験を受けるかどうか悩んでいる段階でも、丁寧に話を聞いてくれるスタッフがそろっているので、気軽に足を運ぶことができます。
たとえば、ある支援センターでは「未経験だけど保育士になりたい」という方のために、実際の園での“体験保育”を紹介してくれる制度もあります。
現場を知ったうえで判断できるので、不安が軽くなり、進むべき方向が見えてきます。
また、地域によっては保育士資格を持つ人の再就職支援も行っており、ブランクのある方への研修や職場体験の機会が設けられていることもあります。
保育士支援センターは、国や自治体が設けている公式の相談窓口なので、安心して利用できます。
費用もかからず、専門の担当者が親身になって話を聞いてくれる場所は、決して一人ではないと感じさせてくれます。
まずは「相談してみる」という一歩から、夢に向かう道が開けていきます。
転職前に知っておきたいこと
保育士への転職を考えるとき、心構えとして知っておきたいことがあります。
それは、「子どもが好き」という気持ちだけでは続けるのが難しい場面もある、ということです。
けれどその一方で、「子どもが好き」という思いがあるからこそ、乗り越えられる瞬間もたくさんあります。
保育の仕事には、体力的な負担や人間関係、行事準備、保護者対応など、目には見えにくい苦労もつきものです。
たとえば、慣れない環境で子どもたちの名前を覚えたり、一人ひとりの個性に合わせた対応を考えたりすることは、想像以上にエネルギーが必要です。
また、仕事の時間以外にも、記録や準備、職員同士の打ち合わせなど、表に出ない業務も多くあります。
それでも、子どもたちの笑顔や小さな成長をそばで見守れるこの仕事は、ほかにはない大きなやりがいを感じさせてくれます。
転職前には、実際の保育現場を見学したり、経験者の話を聞いたりすることで、「現実の保育」の姿にふれることが大切です。
また、自分自身のペースで無理なく学び、段階を踏んで挑戦していくことが、長く働くうえでの土台になります。
保育士として働くということは、毎日を子どもと共に生きるということ。
その一歩を踏み出す前に、しっかりと「自分らしい働き方」を考えておくことが、より良いスタートにつながります。
保育士になって本当によかった。心からの気持ち
毎日が学びと感動の連続
保育士として働くようになってから、毎日が「気づき」と「感動」であふれています。
決まった通りの毎日はなく、子どもたちの表情や言葉に応じてその日の空気が変わっていきます。
そのひとつひとつが、私にとって大切な学びの時間です。
子どもたちは、とても素直でまっすぐな心を持っています。
その純粋さにふれたとき、自分がどれだけ偏った見方をしていたか、どれだけ急ぎすぎていたかに気づかされることもあります。
たとえば、けんかをした後に泣いていた子が、自分の言葉で「ごめんね」と伝えることができた日。
その姿を見て、「成長の瞬間に立ち会えることって、なんて尊いのだろう」と感じました。
保育士という仕事は、教えるだけではなく、気づかされることの連続です。
子どもと一緒に笑い、悩み、寄り添いながら、私自身も人として少しずつ成長させてもらっています。
毎日が同じようで、まったく同じ日は一日もない。
その連続こそが、保育士という仕事のいちばんの魅力だと、私は思っています。
子どもたちから教わること
保育士は子どもにいろいろなことを教える立場に見えるかもしれません。
けれど実際には、子どもたちから教わることの方が、ずっと多いと日々感じています。
子どもたちは、小さなことにも大きく心を動かし、何でも全力で楽しもうとする力を持っています。
その姿を見ていると、「大人になって忘れてしまっていた大切なこと」を思い出させてくれるような気がします。
たとえば、雨上がりの園庭で、水たまりを見つけて無邪気に飛び跳ねる子どもたちの笑顔。
私はその光景に、心からの“今を生きる喜び”を教えられました。
「きれいな服が汚れたらどうしよう」なんて気にせず、ただ目の前の楽しさに夢中になれる純粋さは、大人にこそ必要な力かもしれません。
また、失敗してもすぐに立ち直るたくましさや、相手を思いやるやさしさも、子どもたちは自然と身につけています。
そのやわらかい感性にふれるたび、「私もこうありたい」と、思わされるのです。
子どもたちは、言葉だけでは語れない“生きる力”を教えてくれます。
その存在が、私にとってのいちばんの先生です。
「ありがとう」と言える仕事
保育士という仕事は、「ありがとう」があふれる場所だと、日々感じています。
子どもたち、保護者、同じ園で働く仲間――どの関係のなかにも、感謝の気持ちが自然に生まれてくる場面があります。
その言葉の一つひとつが、私の心をあたため、支えてくれています。
子どもたちからは、毎日のように小さな「ありがとう」をもらいます。
着替えを手伝ったとき、お絵かきを見て「じょうずって言ってくれてありがとう」と笑ったとき、その素直な言葉に何度も救われてきました。
たとえば、ある日お迎えに来たお母さんが「先生、朝泣いていたのに、今日一日笑顔で過ごせたって聞いて安心しました。ありがとうございます」と言ってくれたことがありました。
その一言に、「私の関わりが、少しでも誰かの力になれたんだ」と心から思えました。
また、同じ保育士仲間とのあいだでも、「助かったよ」「ありがとう」「おつかれさま」という言葉が自然と飛び交います。
そのやさしいやりとりが、忙しい毎日の中でも安心できる空気をつくってくれています。
保育士は、誰かのそばで支える仕事ですが、自分もまた多くの人に支えられていることを実感できる仕事です。
「ありがとう」と言ってもらえること、そして「ありがとう」と言いたくなる毎日が、この仕事の何よりの魅力だと私は思っています。
過去の自分に伝えたい「希望はかなうよ」
もしも、幼いころの私に声をかけられるとしたら、まっさきに伝えたい言葉があります。
「大丈夫、あなたの希望はちゃんとかなうよ」――この言葉を、何度も不安になった自分に届けたいと思います。
保育園に通えなかった日々、働く母の姿を見て何もできなかった無力さ、夢を語ることにためらいを感じていた高校時代。
あの頃は、夢がどれほど遠くにあるのかも分からず、ただ漠然と「なれたらいいな」と願うことしかできませんでした。
でも今、保育士として子どもたちのそばにいられる毎日は、その時の小さな願いの積み重ねが導いてくれた結果だと、心から思います。
たとえば、あの日泣いていた小さな私に「あなたの経験は、きっと誰かの力になるよ」と伝えてあげられたら、少しだけ安心できたかもしれません。
過去のつらさや悩みも、夢への一歩だったと今ならわかります。
夢は、すぐにかなわなくてもいい。
遠回りしても、迷っても、途中で立ち止まってもいい。
それでも、自分を信じてあきらめなければ、希望はちゃんと形になります。
過去の自分へ、そして同じように夢を追いかけているすべての人へ。
「だいじょうぶ、ちゃんと届くから」――そう伝えたい気持ちで、今の私がここにいます。
これから保育士を目指すすべての人へ、エールを込めて
保育士になりたい――その想いを抱いたあなたへ。
今、胸の中にあるその気持ちは、どんなに小さくても、どんなに不安をともなっていても、とても尊く、まっすぐな願いです。
その想いがある限り、あなたはもう夢に向かって歩き始めています。
道の途中には、迷いも、立ち止まりたくなる日もあるかもしれません。
でも、子どもたちの未来を支えるこの仕事は、まっすぐで、あたたかくて、なによりもやりがいに満ちた道です。
そして、その道には、あなたのように誰かの力になりたいと願う人の居場所が、ちゃんとあります。
私は、何度も悩み、何度も不安になりながらも、子どもたちの笑顔に支えられてここまできました。
「ありがとう」と言ってもらえた日、「先生だいすき」と手をつないでくれた日。
そうした瞬間が、この道を選んで本当によかったと思わせてくれました。
もしあなたが、誰かの力になりたいと思ったことがあるなら。
もしあなたが、子どもの笑顔に心が動いたことがあるなら。
その気持ちは、きっと保育士として誰かを支える力になります。
今のあなたに、私から心からのエールを送ります。
「あなたの歩みは、きっと子どもたちの未来を明るく照らします」
どうかその一歩を、大切に、大切に進んでください。
夢は叶うよ。