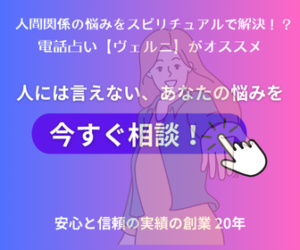インデックス
Aさんの悩み――「なんでこんなことで怒られたの?」
若手社員Aさんが経験した初めての異文化上司
外国人上司との最初の出会いは、多くの若手社員にとって戸惑いの連続になる。
なぜなら、日本の職場文化に慣れた環境から一転して、価値観やコミュニケーションの前提がまったく異なるからである。
たとえばAさんは、入社3年目で初めて外国人の上司Bさんのチームに配属された。
Bさんは欧州出身で、部下の自主性を重んじるタイプだったが、Aさんにはその期待が伝わらず、常に「もっと積極的に動いて」と言われてばかりいた。
日本の上司であれば細かく指示してくれていた部分を、Bさんは何も言わずに任せる。
それが信頼の証とは気づかず、Aさんは「何をしていいかわからない」「怒られるのが怖い」と感じていた。
異文化の上司との関わりは最初は戸惑いが多いが、それは新しい価値観に触れる最初の一歩である。
「空気を読む」文化は通じない?初めてのすれ違い
日本では「空気を読む」ことが美徳とされるが、外国人上司にはその価値観が通じないことが多い。
なぜなら、多くの外国人は「言葉にしないと伝わらない」という文化で育っているからである。
Aさんは、会議中に「上司の表情が険しいから、この案はやめておこう」と感じ、自分の意見を言うのをやめた。
ところが後日、「どうして何も言ってくれないの?」と上司から注意された。
Aさんにとっては気を遣ったつもりでも、上司から見れば「協力的でない」と映ったのだ。
たとえば欧米では、沈黙や遠慮は「意見がない」と解釈されやすい。
Aさんのように、言わないことが思いやりとされる文化で育った人には、このギャップが強いストレスになる。
空気を読むことが通じない場面では、逆に「はっきり伝える」姿勢が信頼につながる。
「自分が悪いのかな…」と感じてしまった毎日
異文化の中で思うように評価されないと、つい自分を責めてしまうことがある。
なぜなら、文化の違いによるすれ違いを「自分の能力不足」と誤解してしまいやすいからである。
Aさんは、上司に何度も「もっと自分の考えを言ってほしい」と言われるうちに、「自分には主体性が足りないのでは」と思い込むようになった。
しかし実際には、Aさんの仕事ぶり自体には問題はなく、単に「伝え方のスタイル」が上司の期待とずれていただけだった。
たとえば、Aさんは上司が求めるほど積極的に発言しなかったが、資料の準備や裏方の作業には細やかに気を配っていた。
それを上司は評価する機会がなく、誤解が続いていたのである。
文化の違いによる戸惑いは、自分のせいと決めつけず、「どこがすれ違っているのか」を見つめ直すことが大切である。
外国人上司Bさんの本音――「なんで何も言ってくれないの?
「日本人は察してくれる」と思ってない外国人上司
多くの外国人上司は、「部下が察して動く」ことを前提としていない。
なぜなら、自分の意見や希望は言葉にして初めて伝わるという文化で育っているからである。
Bさんも最初、日本人の部下たちがあまり発言せず、積極的に提案もしない様子に困惑していた。
何か不満があるのか、仕事に興味がないのかと受け取ってしまったという。
Bさんにとっては「問題があれば言ってくるだろう」という考えが当然だったため、沈黙は理解しにくかった。
たとえば、欧州やアメリカでは、部下が上司に対しても意見を言うのが普通である。
それが信頼関係の証であり、仕事への意欲とみなされる。
外国人上司は、察してくれるとは思っていないからこそ、日本の「気配り」をうまく受け取れないことがある。
沈黙=拒否?文化が違えば受け取り方も真逆に
沈黙が意味するものは、文化によってまったく異なる解釈をされる。
なぜなら、沈黙に込める意図は国や価値観によって大きく異なり、そこにすれ違いが生まれるからである。
Bさんはある会議で、日本人の部下が黙ったままだったことに対し、「このプロジェクトに反対しているのか?」と受け取ったという。
しかし実際には、部下たちは「上司の意見を尊重して黙っていた」だけだった。
たとえば、日本では沈黙は「同意」や「配慮」を意味することが多いが、欧米の職場では沈黙は「納得していない」「意見がない」などネガティブなサインとされやすい。
沈黙に対する解釈の違いを知っておくことで、意図しない誤解を減らすことができる。
「オープンに言ってほしい」Bさんの戸惑いと本音
外国人上司の多くは、「率直に意見を伝えてほしい」と強く願っている。
なぜなら、仕事の現場では感情よりも事実や改善点を共有することが優先される文化が多いからである。
Bさんは、部下がなかなか自分の考えや困っていることを話してくれない状況に対し、「どうして話してくれないんだろう」と悩んでいた。
本人は気軽に相談してほしいという気持ちで接していたが、部下から見ると「厳しくて話しかけづらい人」と映っていた。
たとえば、Bさんは「言いたいことがあるなら直接言ってくれた方が嬉しい」と何度も伝えていたが、日本の部下は「遠慮」や「失礼に思われるかも」という不安から踏み出せずにいた。
率直さを大切にする文化においては、言葉にしなければ何も伝わらないという前提がある。
だからこそ、勇気を持って言葉にすることが信頼構築への第一歩となる。
渡勇太郎さんのアドバイス――「文化の違いは、怖くない」
違いは「壁」じゃなく「学び」に変えられる
異文化との違いは、乗り越えるべき「壁」ではなく、新しい考え方を得られる「学び」の機会である。
なぜなら、自分の当たり前が通じない状況に直面することで、視野が広がり、柔軟な思考力が身につくからである。
渡勇太郎さんは、これまで10カ国以上で働いてきた経験から、「文化の違いに最初は戸惑っても、そのたびに自分自身がアップデートされた」と語っている。
たとえば、話を遮ることが失礼ではない国や、逆に目を見て話すのが無礼とされる地域など、それぞれの背景を知ることで、相手への理解が深まり、対応力も自然と高まっていったという。
異文化の違いを恐れるのではなく、それを通して自分を磨くチャンスと捉えることができれば、職場でのストレスも少なくなる。
「YES」も「NO」も、ハッキリ伝える勇気を持とう
外国人上司と信頼関係を築くには、「YES」も「NO」も自分の言葉でしっかり伝えることが大切である。
なぜなら、はっきりとした意思表示が、相手にとって安心材料になるからである。
渡勇太郎さんは、「曖昧な返事が一番相手を不安にさせる」と話す。
たとえば、「考えておきます」や「難しいかもしれません」といった言い回しは、日本では丁寧でも、他の文化圏では「断られたのか承諾されたのかわからない」と感じられてしまう。
実際、YESなのかNOなのか明確に答えることで、次の行動を相手が取りやすくなり、仕事の進行がスムーズになる。
たとえば、「このスケジュールは間に合いません」ときっぱり言えば、上司は別の手を打つことができる。
自分の立場を守る意味でも、「伝える勇気」を持つことが、異文化の中では非常に重要である。
「困ったら、頼っていい」信頼を築く一歩とは
異文化コミュニケーションにおいて、困ったときは一人で抱え込まず、素直に助けを求めることが信頼関係の第一歩になる。
なぜなら、相手を信頼しているからこそ相談できるという行為が、むしろ信頼を深めるきっかけになるからである。
渡勇太郎さんは、海外で働いていた頃、言語や文化の壁で理解できないことがあったとき、「恥をかくより、聞くことの方がずっと良い」と教わったという。
たとえば、ある会議で専門用語の意味がわからずに手を挙げて質問したところ、「君のその姿勢が素晴らしい」と逆に評価された経験もある。
日本では「聞く=迷惑をかける」と考えがちだが、異文化の職場では「聞かない方が失礼」とされることもある。
困ったときに助けを求めることは、相手との信頼を深めるきっかけになるだけでなく、自分自身の成長にもつながる。
文化に「正解」はない、だからこそ柔軟さが大事
異文化の中では「どの文化が正しいか」を判断すること自体に意味はなく、むしろ柔軟に受け止める姿勢が大切になる。
なぜなら、文化とは長い歴史や環境の中で形づくられてきた価値観であり、一つの基準では測れないからである。
渡勇太郎さんは、「正しい・間違っているではなく、違いをどう活かすかが重要」と話す。
たとえば、時間の感覚ひとつ取っても、厳密に守る国もあれば、柔軟に考える国もある。
それぞれが持つ背景や価値観を知ることで、相手の行動に意味を見出せるようになる。
違いに直面したときに、「理解できない」と拒絶するのではなく、「こういう考え方もあるのか」と受け入れることで、対話が生まれやすくなる。
文化には唯一の正解はなく、多様な考え方を受け入れる柔軟さが、異文化の中で自分らしく働くための鍵となる。
Aさんが変われた、4つの行動
1. 言葉にして伝える「小さな習慣」を持つ
文化の違いによる誤解を減らすには、「思っていることを言葉にする習慣」を持つことが大きな効果をもたらす。
なぜなら、相手が何を考えているかを「察する」ことが期待されない文化では、自分の意見や感情を言葉で伝えなければ理解されないからである。
Aさんは以前、上司からの指示に対して無言でうなずくだけだったが、それでは伝わらないことを知ってからは、「承知しました」「わからない部分があります」など、短くても言葉にするよう心がけるようになった。
たとえば、朝のミーティングで「この点についてどう思う?」と聞かれた際も、「今の段階では〇〇と考えています」と自分なりの答えを返すようになった。
こうした小さな習慣を積み重ねることで、相手との距離感が縮まり、信頼感も少しずつ生まれていく。
2. 自分の文化も「説明」してみる
異文化でのコミュニケーションでは、相手の文化を理解するだけでなく、自分の文化についても説明する姿勢が大切である。
なぜなら、「なぜその行動を取るのか」を伝えることで、誤解が減り、相互理解が深まるからである。
Aさんは、外国人上司に対して、自分が発言を控える理由を「日本では上司の意見をまず尊重するのが礼儀とされている」と説明したところ、上司がその背景を理解し、「では、私から先に意見を聞くね」と言ってくれるようになった。
たとえば、会議の場でも、先にAさんが「日本ではこんな考え方があります」と前置きすることで、上司がより柔軟に受け止めてくれるようになった。
自分の文化を伝えることは、相手に歩み寄ってもらうための第一歩となる。
3. 上司のリアクションを怖がらない
異文化の上司と接するうえで重要なのは、相手のリアクションを過剰に恐れずに向き合うことである。
なぜなら、文化によって表情や口調が異なっても、感情の内容までは同じとは限らないからである。
Aさんは、Bさんの表情が険しくなるたびに「怒られているのでは」と思っていたが、後にBさんは「考えていただけで、別に怒っていないよ」と笑って話してくれた。
たとえば、欧米では議論中に真剣な顔つきになるのは当たり前であり、それは思考中のサインにすぎない。
文化の違いを理解してからは、Aさんは相手の表情に過敏にならず、「言葉としてどうだったか」を重視するようになった。
表面的な反応にとらわれず、冷静に対話を続ける姿勢が、異文化の中では信頼構築につながる。
4. 気になることは「聞いてみる」をルールにする
異文化の中では、わからないことや疑問に感じたことをそのままにせず、「聞いてみる」ことを習慣にすることが大切である。
なぜなら、文化の違いによる誤解は、放置すればするほど大きくなり、関係性の悪化につながるからである。
Aさんは、以前なら聞くのをためらっていたようなことも、「これはどういう意味ですか?」「どう進めればいいですか?」と率直に尋ねるようになった。
その結果、上司の期待や意図が明確になり、行動しやすくなったという。
たとえば、ミーティング後に「今の内容で重要なポイントはどこですか?」と聞くだけで、認識のズレを防ぐことができる。
「聞いてみる」というルールは、相手への敬意と前向きな姿勢を伝える手段でもある。
変わったのは関係性だけじゃない、自信もついた
異文化に向き合う中で変わったのは、上司との関係性だけでなく、Aさん自身の「自己信頼感」だった。
なぜなら、相手に合わせようとするだけでなく、自分の考えを伝えることに慣れることで、自分の価値を再認識できたからである。
Aさんは当初、言葉にすることや目を見て話すことに不安を感じていたが、小さな実践を積み重ねる中で、「伝えること=怖いこと」ではなく「前向きな行動」だと気づけるようになった。
たとえば、少し勇気を出して発言したミーティングで、上司から「それはとても良いアイデアだ」と評価された経験が自信につながった。
文化の違いを越えて通じ合えた経験は、仕事への意欲にもつながり、Aさんの働き方そのものを変えていった。
まとめ――あなたの悩みは、あなた一人のものじゃない
「戸惑い」は誰にでもある、でもそれは前進のサイン
異文化との関わりで感じる「戸惑い」は、決して後ろ向きなものではなく、むしろ前に進んでいる証である。
なぜなら、違いに直面して悩むということは、自分の枠を超えて新しい環境に向き合っているからである。
渡勇太郎さんも、海外での最初の仕事では、会話のテンポやジョークの意味がわからず戸惑ったと語る。
しかし、その不安を経験したからこそ、相手の文化を学び、自分の伝え方を工夫するようになったという。
たとえば、相手の反応を観察し、少しずつ話し方を調整することで、やがて自然に会話ができるようになった。
戸惑いは、自分が新しいステージに立っている証拠であり、変化への一歩を踏み出しているサインでもある。
「違う」は「間違い」じゃない
異文化における考え方や行動の「違い」は、決して「間違い」ではないという視点が大切である。
なぜなら、文化はそれぞれが築いてきた歴史や価値観に根ざしており、単純な正誤では測れないからである。
渡勇太郎さんは、国によって仕事の進め方も大きく異なることを実感してきた。
たとえば、ある国では「早く進める」ことが最優先される一方で、別の国では「丁寧に確認する」ことが重視される。
そのどちらも、その文化にとっては正当な判断基準である。
違いを見たときに「おかしい」と感じるのではなく、「なぜそうなのか」と考えることで、視点が広がり、理解が深まっていく。
異文化との出会いでは、違いに戸惑うよりも、その背景を知る姿勢が求められる。
あなたのその気持ちを、私たちは理解しています
外国人上司との文化の違いに悩んでいるあなたの気持ちは、決して一人だけのものではない。
なぜなら、多くの人が同じような戸惑いやストレスを経験しながら、少しずつその壁を乗り越えているからである。
渡勇太郎さん自身も、最初から異文化に慣れていたわけではない。
伝えたいことが伝わらなかったり、誤解されたりする経験を何度も重ねてきた。
しかしそのたびに、「一人で抱え込まない」「違いを受け入れる」ことで、前に進むことができたと語る。
今、あなたが感じている不安や疑問は、異文化に向き合っている証拠であり、それは成長の入り口でもある。
私たちは、その気持ちの大切さを理解しているからこそ、あなたの一歩を心から応援している。